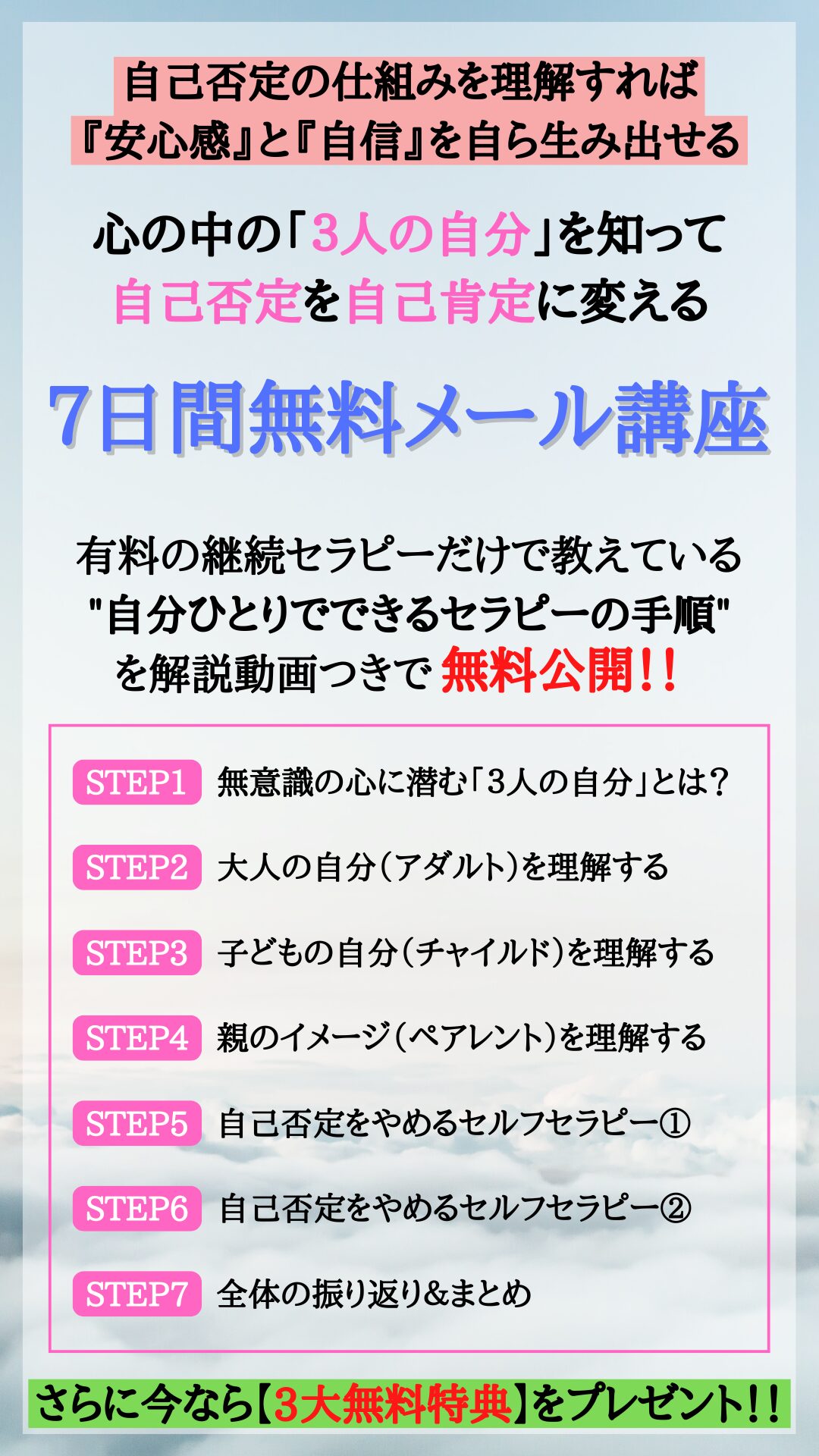目次
- 1 愛着障害とは
- 1-1 愛着行動と安全基地
- 1-2 愛着障害=愛着行動が不安定な人
- 2 愛着障害を抱えた大人の特徴
- 3 愛着行動の3つのスタイル
- 4 愛着障害を克服するカギは「安全基地」
- 4-1 安全基地の形成に必要な5要素
- 5 愛情の傷は愛情で癒やせる
こんにちは。
心理セラピストの
大野貴之です。
あなたは「愛着障害」という言葉を聞いたことはありますか?
言葉自体は聞いたことあるけどよく知らない方から今まさに愛着障害による生きづらさに悩んでいる方など、色々な方がいらっしゃると思います。
そこで本記事では、愛着障害の特徴・直し方などをまとめてご紹介します。
愛着障害について知りたい方は、ぜひ気になる所だけでもお読みください。
愛着障害とは
愛着障害とは、『0歳~3歳までに養育者との間に「安全基地」が築かれなかった場合に、その後の人生において「愛着行動」が不安定になる症状』です。
ただ、この説明だけではなかなかピンと来ませんよね。
まずは「安全基地」「愛着行動」といった言葉の意味からもう少し細かく見ていきましょう。
愛着行動と安全基地
子ども(人)はストレスや不安を感じた時、自分を守ってくれる存在(主に母親)に触れたりそばにいてもらうことで安心感を得ます。
この安心感を得ようとする行動が「愛着行動」です。
また、子どもは愛着行動を何度も繰り返すことでその人との愛着の絆を深めていき、次第にその人本人がいなくても自ら安心感を作り出せるようになっていきます。
この安心感を自ら生み出せる状態を「安全基地が築かれた状態」と呼びます。
愛着障害=愛着行動が不安定な人
しかし、子どもが愛着行動を取っても応えてくれなかったり、そもそも愛着行動を取る相手がいないような環境に長く身を置くと、次第に子どもの愛着行動は不安定になっていきます。
例えば、ある時は応えてくれるけどある時は不機嫌な顔をされるなどの経験を繰り返した子どもは、応えてくれるかわからない不安から愛着行動が過剰になるかもしれません。
また、愛着行動を取る対象がいつもそばにいない、いても応えてくれないといった環境に長く身を置くと、そもそも愛着行動を取らなくなってしまう可能性もあります。
そして愛着行動が不安定なまま大人になった子供は、対人関係で人に嫌われる不安を覚えたり(不安型)、そもそも対人関係を築こうとしなかったり(回避型)します。
これが「愛着障害」です。
愛着障害を抱えた大人の特徴

では愛着障害を抱えた大人にはどんな特徴があるんでしょう?
愛着とは、簡単に言うと「人と人の絆を結ぶ能力」です。
愛着が安定している人は他人とほどよい距離感を作ることができ、
- 自分の意見を主張できる
- 嫌なことはNOと言える
- 困った時は助けを求められる
など、他人と信頼関係をうまく築きつつストレスからもうまく身を守ることができます。
他人との距離感が不安定になりがちです。
- 嫌われるのが不安で意見が言えない
- 人に好かれようと相手に合わせすぎる
- そもそも人との関わりを避ける
など、他人と信頼関係を築きにくいだけでなく、対人関係によって多くのストレスを抱え込んでしまいます。
また、そういったストレスを避けようと初めから人との関わりを避ける人もいますが、根本にあるのは「人との距離感がわからない」といった同じ原因から来ています。
愛着行動の3つのスタイル

「愛着障害とは」の章でも説明しましたが、こういった行動を取ってしまう原因は愛着行動の不安定さにあります。
ここではこの「愛着行動」について大きく3つのスタイルにわけてご説明します。
安定型
まず1つ目は「安定型」です。
このスタイルの人はストレスや不安を感じた時に適度な愛着行動を取ることができ、他人との信頼関係も上手に築くことができます。
不安型
2つ目のスタイルは「不安型」です。
このスタイルの人は「人に嫌われていないかどうか」を一番に気にします。
仕事・プライベートに関わらず相手の顔色がいつも気になり、相手を不快にさせないような言動や行動に気を遣います。
ただし、相手がこちらの思うような反応を得られない場合に「怒らせてしまった?嫌われた?」と強い不安とストレスを感じることも。
こちらが気にするほど相手はこちらの反応を気にしていないことも多く、気遣いばかりが空回りしやすいのが不安型スタイルの特徴です。
不安型の人は子どもの頃に甘やかされる一方で、意にそぐわない時は強く否定される両極端な扱いを受けている場合が多くあります。
そのため「愛情を求めたい」気持ちと「いつ拒否されるかわからない」気持ちを両方抱えており、それが「人から嫌われる不安」を強めています。
回避型
最後に3つ目のスタイルは「回避型」です。
このスタイルの人は心理的にも物理的にも距離のある対人関係を好み、「誰にも縛られたくない」という強い願望があります。
また、それと同時に「葛藤を抱えるのが苦手」といった特徴があります。
他人との意見の食い違いなど、人とぶつかり合う(=葛藤)状況が苦手なため最初から積極的な人との関わりを避ける傾向にあります。
回避型の人は子どもの頃に十分な愛着行動を取らせてもらえなかった人です。
そのため、「どうせ求めても手に入らないなら最初から求めない」といった気持ちを抱えており、他人に積極的に関与しないことで自分を守っているとも言えるでしょう。
※愛着スタイルについてはこちらの記事でも詳しく解説しています↓
愛着障害を克服するカギは「安全基地」

最後に「愛着障害」を克服する方法をご紹介します。
愛着障害とは、子どもの頃に「安全基地」が築かれなかったことで大人になってからも「愛着行動」が不安定になること。
つまり、愛着障害を克服するためには「安全基地」の築き直しが必要となります。
しかし、本来「安全基地」は母親などの自分を守ってくれる存在との間に愛着の絆を築くことで作られるもの。
それを大人になってから一人で作ることは残念ながらできないんです。
そのため、愛着障害を克服するためには、自分を否定される不安を感じずに何でも話せるような存在との出会いが極めて重要。
そういった存在が仮の「安全基地」として機能すれば、徐々に自分の愛着行動が安定していくでしょう。
安全基地の形成に必要な5要素
大人になってから仮の「安全基地」となってもらう存在は実の両親である必要はありません。
家族・恋人・友人・教師・カウンセラーなど、自分を否定される不安を感じずに何でも話せる相手であれば誰でもいいのです。
ではどんな相手なら安全基地を形成できるのか?そのために必要な5要素をご紹介します。
- 安全性
最も重要な要素で、一緒にいても傷つけられない人 - 応答性
求めた時にちゃんと応えてくれる人 - 共感性
何を求めているか共感してくれる人 - 安定性
気分や都合で対応が変わらず、一貫した対応をしてくれる人 - 誠実さ
一人の人間として心から大切にしてくれる人
愛情の傷は愛情で癒やせる
愛着障害とは、子どもの頃の環境が原因で心に愛情の傷を負っている問題です。
決してその人の人格や能力に問題があるわけではなく、その人の育った環境に問題があっただけです。
そして、愛情の傷は同じく愛情で癒やすことができます。
まずは自分のことを決して否定することなく、安心して何でも話せる相手を探すことから始めてみてください。
どうしても身近にそういった存在がいない方は、専門家の力を借りるのも一つの手。
『ライフチェンジセラピー』では、カウンセリングとコーチングの2つのアプローチで安全基地を育てていきます。
今なら特別価格で体験セッションを受付中ですので、気になる方はぜひお越しくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。